某撮影会に撮影を申し込むと、モデルさんの都合により受けられないとの返事。
おやまあ
フリーのモデルさんなら、完全無視される場合もタマにはあるけれど
代替日の提案もなしにお断りとは、う~ん、これは初めてのパターンだ。
急な用事ができたのか、爺カメラマンはイヤなのか?
ご縁がなかったということで 今回のモデルさんに決定。ゴメンネ。
新規のモデルさんを開拓するのは(モデルさんにとっても同様だが)小心者爺には難関なのです。
気心と技量を知っていると ラクチン♪
せめて場所なりとも新規開拓しようと、GoogleMAPとニラメッコ
古いビルと新しいビルが混ざるこの街にしようか。
中之島から本町にかけては住友村。ここは住友の社交場らしい。
モデルさんへの注文は「ここから出てきたエラソーなお嬢様」
かなたの超高層ビルよりも古臭いビルのほうが好きだなあ。
街角ロケはこんな風に思いもかけない通行人が入るのが楽しい。
なんかよくわからないビルの非常階段。縦構図か横構図か悩んだんだ。
中華料理店の看板で、ここでもエラソーにポーズしてもらいました。
注文は「中国の金持ちのワガママ娘」
いい味のビル前で強烈な西日を浴びて。あ~カメラの設定が難しすぎる・・・
1階は宝石店・2階はイタリア料理店・はてその上は?
フツーの駐車場、右のフェンスの向こう側は土佐堀。
どんなポーズも思いつかず、シェ~(死語) モデルさんには説明もせず♪
右の上段にいい夕日が差してたのですが、出入り禁止・・・
古いビルがすこし混じる通り 旧土佐堀通。(これは単なる風景写真)
土佐堀の中之島側には エー色した壁が続きます。 秋色やね。
暗い表情をお願いするだけでは申し訳ないので、爽やかな1枚もマゼておこう。
肥後橋より南側は人通り少なく、こんな写真が撮り放題。
背中のシワを気にするかどうか。左肩の動きが想像できていいんだが、カメラマンの趣味だな・・・
背中で魅せるモデルさん。
ごく普通の陸橋でも背景がいいと陸橋まで良くみえてくる(モデルさんはどうなんだ?)
前蹴り・後ろ蹴りをしてもらった1枚。廻し蹴りはしていません。
モデルさんの名誉のため言っておきます。これはお願いしたポーズ、決して普段では・・・
お題「来ない彼氏を待つ女」 それらしい現像にしてみました。
劇的な表情はマダマダ! 次回ガンバロー
捨て猫の気分
カメラも現像も変えたのです。 水平垂直のない不安定な構図
ナマイキエーオンナに仕上げてみました。
口紅のついたタバコを落としておけば完璧。
モデルさんに言いました「僕はカワイイのは求めてないネン」
自然なポーズ(放し飼いとも言う)
[ 脱線その1 ] ===========================================================================
江戸時代の橋名が多く残る中之島かいわい。幕府ではなく藩が自費で懸けたとうろおぼえ。
なぜ各藩が自費で橋をかけたか?このあたりは蔵屋敷が集中していたのです。
土佐堀にかかる橋を上流から
栴檀木橋・淀屋橋・錦橋・肥後橋・筑前橋・常安橋・越中橋・土佐堀橋・湊橋・端建蔵橋
青色:藩にかかわるもの
灰色:明治以降のもの
調べました。
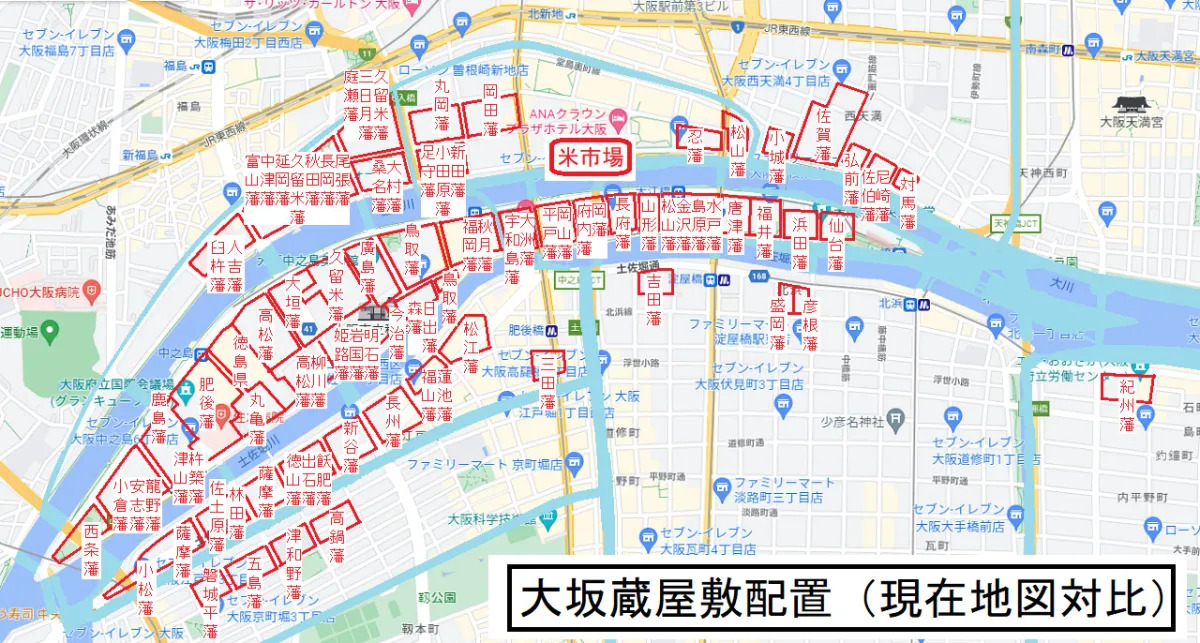
肥後橋なんだから肥後藩(熊本)、おや~蔵屋敷はもっと下流のグランキューブのあたり。
そんなはずはない!この地図がおかしい!
頼りになるのは日文研の地図データベース。
幕末の絵図では蔵屋敷図と同じなので、江戸時代初期1657年の絵図を。
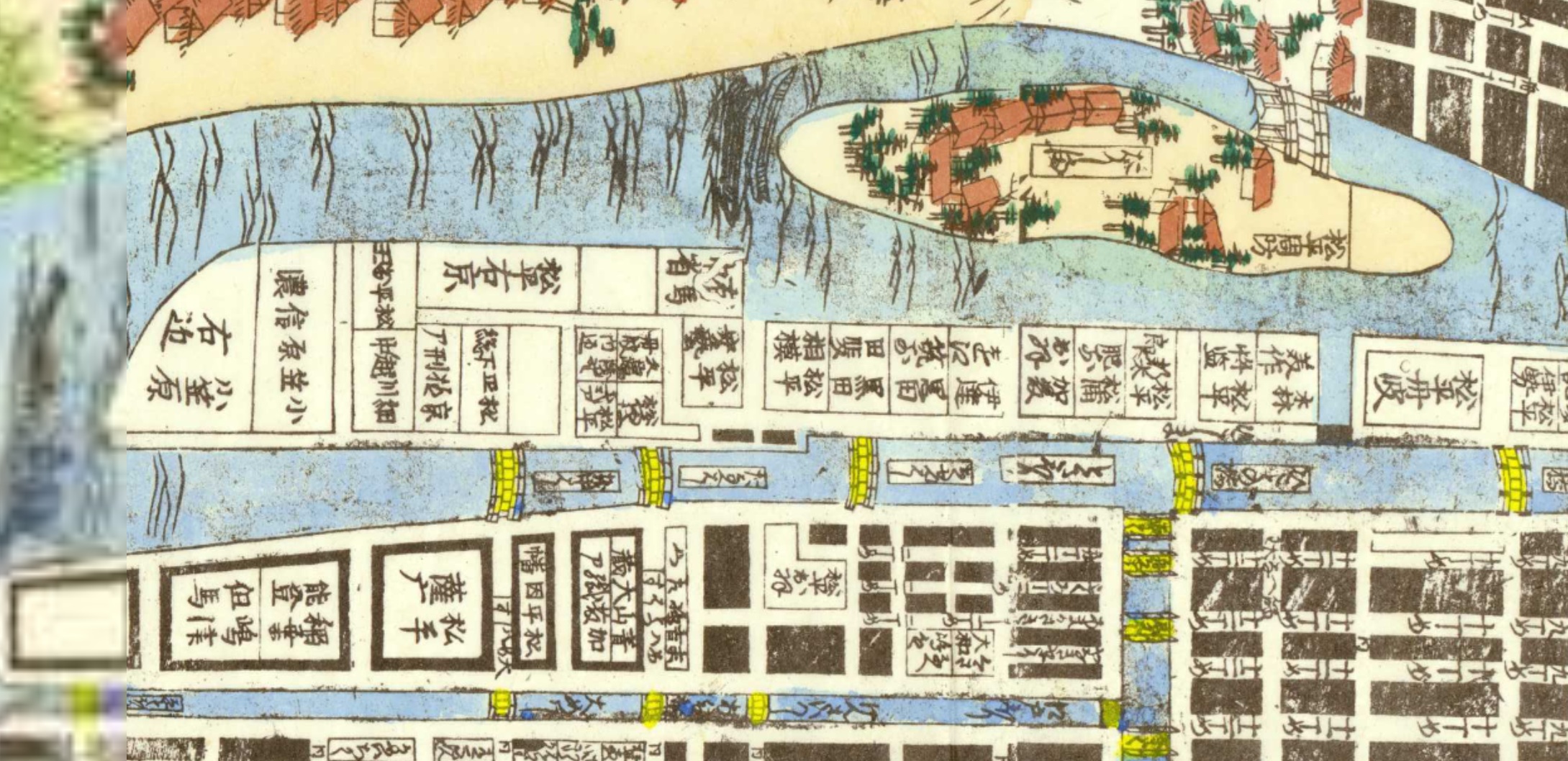
ところが肥後橋の北詰には松平将監の名が。肥後藩ではない。
この人物が何者なのかちょっと調べたくらいでは不明。岩見浜田藩か?
肥後藩は細川家、その名前は下流に細川越中とある。ガラシアの夫忠興ではなくその子か孫のはず。
江戸時代の蔵屋敷の表示は藩名ではなく家名+官職なので極めてヤッカイ。一体誰なんだあ?
グランキューブの近くに越中橋が今もあります。細川越中守から名付けられたのです。
大阪市の説明では 江戸初期には肥後橋北詰に肥後藩蔵屋敷があった。
その後中之島の下流に移転したが、橋名・地名はそのまま残ったと。
肥後藩蔵屋敷が移転したのは江戸初期。はて、一体ナゼ?
失政をしたというわけではなく、肥後橋の蔵屋敷は手狭だったか?
あ~結局肥後橋北詰にあったという絵図は見つからず・・・
あと探す場所は 大阪市立中央図書館・国立国会図書館・国立公文書館
あ~メンドクサイ
[ 脱線その2 ] ===========================================================================
フェスティバルホール 建替え直前に(ホールはすでに閉鎖)地下にあった工事事務所に何度も通った。
設計:日建設計・施工:竹中工務店 爺はその中のホンのチビッとだけ関わった。
どんな超一流の設計事務所でも、完成時の形状・荷重での検討だけで、施工途上のことは考えない。
そこで、出番は施工会社に移り、ワイらしがない設計事務所にも声がかかる。
若いバリバリの設計技術者は今やPCソフトを使いこなすが、こういうゲテモノは不得意。
もちろん、大工務店といえども、全社あげて担当するわけもなく(他にも受注した多数の物件ある)
下請け・外注にたよる部分が必ずある。 ワイのやったのは施工途上の中途半端な形状で
施工重機や仮設時の荷重で安全性を検討すること。
例えば、 1階床にダンプカーやクレーンが走行して大丈夫か?
中層階屋根に高層階足場を乗せてよいか?
大ホールのバルコニーのコンクリート打設重量を下階床で受けてよいか?
カッコイイ建物が出来上がっても、施工会社の名前が出ることは稀、下請けの名前など出るわけもない。
同様に膨大な数の職員・職人が関わっているが、それは本人の胸の内にしか残らない。
まあ職人なんてはるか昔からそういうもの。名前を残そうなんてイカガワシイ。
江戸時代の橋名が多く残る中之島かいわい。幕府ではなく藩が自費で懸けたとうろおぼえ。
なぜ各藩が自費で橋をかけたか?このあたりは蔵屋敷が集中していたのです。
土佐堀にかかる橋を上流から
栴檀木橋・淀屋橋・錦橋・肥後橋・筑前橋・常安橋・越中橋・土佐堀橋・湊橋・端建蔵橋
青色:藩にかかわるもの
灰色:明治以降のもの
調べました。
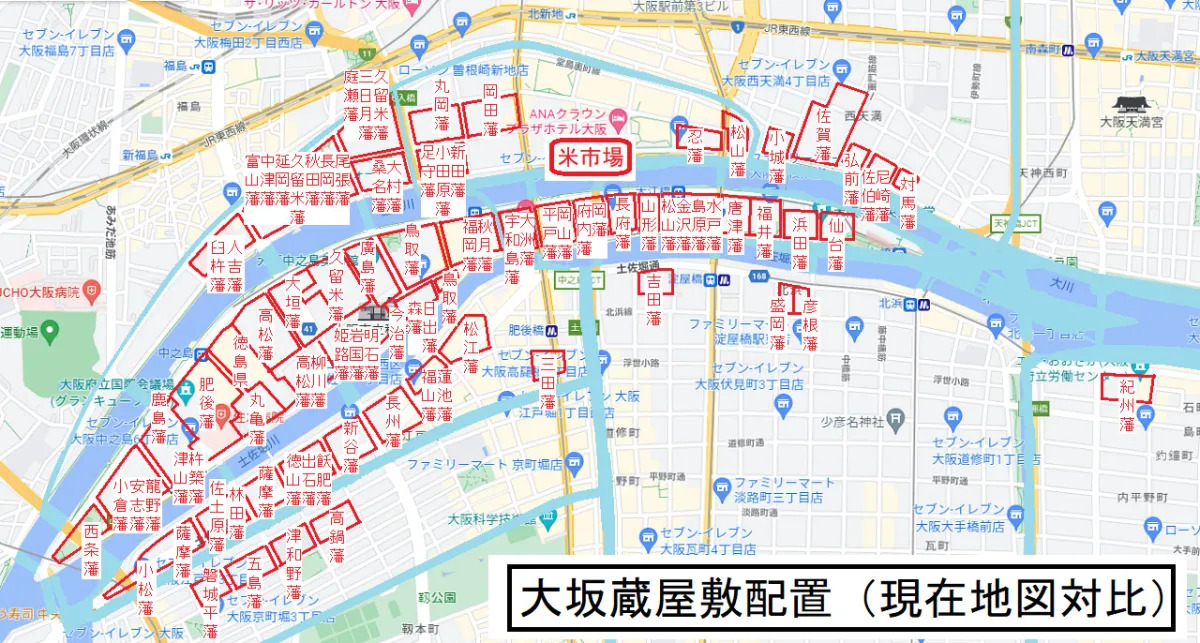
肥後橋なんだから肥後藩(熊本)、おや~蔵屋敷はもっと下流のグランキューブのあたり。
そんなはずはない!この地図がおかしい!
頼りになるのは日文研の地図データベース。
幕末の絵図では蔵屋敷図と同じなので、江戸時代初期1657年の絵図を。
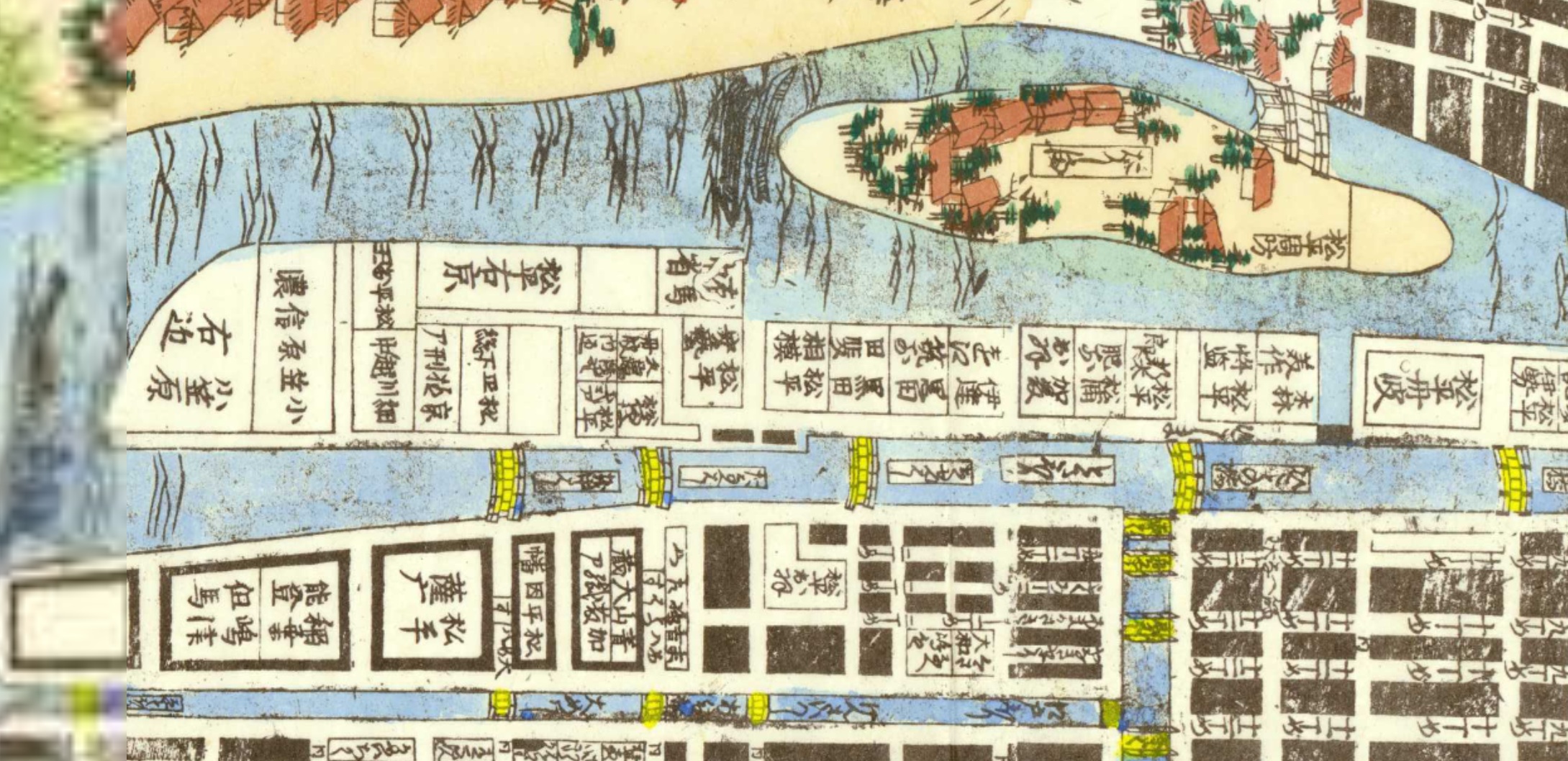
ところが肥後橋の北詰には松平将監の名が。肥後藩ではない。
この人物が何者なのかちょっと調べたくらいでは不明。岩見浜田藩か?
肥後藩は細川家、その名前は下流に細川越中とある。ガラシアの夫忠興ではなくその子か孫のはず。
江戸時代の蔵屋敷の表示は藩名ではなく家名+官職なので極めてヤッカイ。一体誰なんだあ?
グランキューブの近くに越中橋が今もあります。細川越中守から名付けられたのです。
大阪市の説明では 江戸初期には肥後橋北詰に肥後藩蔵屋敷があった。
その後中之島の下流に移転したが、橋名・地名はそのまま残ったと。
肥後藩蔵屋敷が移転したのは江戸初期。はて、一体ナゼ?
失政をしたというわけではなく、肥後橋の蔵屋敷は手狭だったか?
あ~結局肥後橋北詰にあったという絵図は見つからず・・・
あと探す場所は 大阪市立中央図書館・国立国会図書館・国立公文書館
あ~メンドクサイ
[ 脱線その2 ] ===========================================================================
フェスティバルホール 建替え直前に(ホールはすでに閉鎖)地下にあった工事事務所に何度も通った。
設計:日建設計・施工:竹中工務店 爺はその中のホンのチビッとだけ関わった。
どんな超一流の設計事務所でも、完成時の形状・荷重での検討だけで、施工途上のことは考えない。
そこで、出番は施工会社に移り、ワイらしがない設計事務所にも声がかかる。
若いバリバリの設計技術者は今やPCソフトを使いこなすが、こういうゲテモノは不得意。
もちろん、大工務店といえども、全社あげて担当するわけもなく(他にも受注した多数の物件ある)
下請け・外注にたよる部分が必ずある。 ワイのやったのは施工途上の中途半端な形状で
施工重機や仮設時の荷重で安全性を検討すること。
例えば、 1階床にダンプカーやクレーンが走行して大丈夫か?
中層階屋根に高層階足場を乗せてよいか?
大ホールのバルコニーのコンクリート打設重量を下階床で受けてよいか?
カッコイイ建物が出来上がっても、施工会社の名前が出ることは稀、下請けの名前など出るわけもない。
同様に膨大な数の職員・職人が関わっているが、それは本人の胸の内にしか残らない。
まあ職人なんてはるか昔からそういうもの。名前を残そうなんてイカガワシイ。